第3次障害者プラン・概要版
第3次秋田市障害者プランは
障害者基本法に基づく「障害者計画」と障害者自立支援法に基づく「障害福祉計画」を一体のものとして策定された、本市障害者福祉施策の全体像を示すものです。
「第11次秋田市総合計画」を最上位計画とし、「秋田市高齢者プラン」「秋田市次世代育成支援行動計画」「健康あきた市21計画」とともに、本市保健福祉施策の部門計画として位置づけられます。
計画期間は、平成19年度から国の障害者基本計画の最終年度である平成24年度までの6年間であり、「障害福祉計画」としては、平成19年度から20年度を第一期計画とし、平成20年度に見直しを行った上で、平成21年度から23年度を第二期計画とします。
基本理念・施策の体系
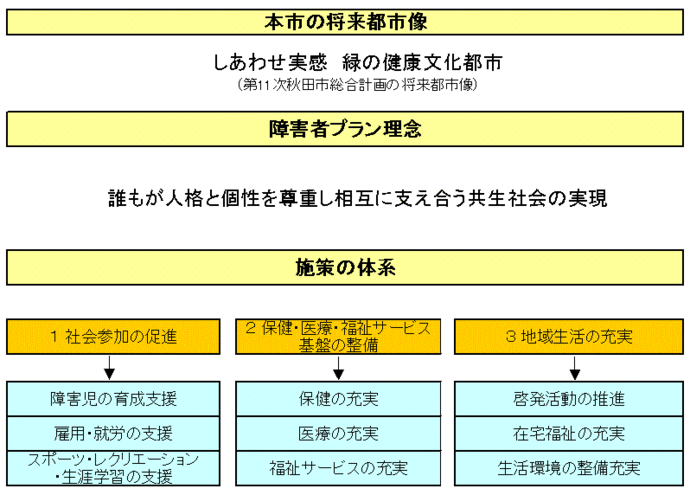
「誰もが人格と個性を尊重し相互に支え合う共生社会の実現」とは
平成14年12月に策定された国の障害者基本計画における基本的な方針の考え方から、「誰もが人格と個性を尊重し相互に支え合う共生社会」をプランの基本理念としました。
国の障害者基本計画は、「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の理念を継承するとともに、障害者の社会参加、参画に向けた施策の一層の推進を図るため、今後10年間に講ずべき障害者施策の基本的方向について定めたものです。
障害者基本計画-基本的な方針(考え方)抜粋
21世紀に我が国が目指すべき社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会とする必要がある。
共生社会においては、障害者は、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員としてその責任を分担する。
他方、障害者の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除去するとともに障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援することが求められる。
人権が尊重され能力が発揮できる社会の実現を図ることは、少子高齢化の進展する我が国において、将来の活力を維持向上させる上でも重要である。
国民誰もが同等に参加、参画できる共生社会は、行政だけでなく企業、NPO等すべての社会構成員がその価値観を共有し、それぞれの役割と責任を自覚して主体的に取り組むことにより初めて実現できるものであり、国民一人一人の理解と協力を促進し、社会全体としてその具体化を着実に推進していくことが重要である。
本市の障害者人口の将来推計
総人口が減少に転じる一方、障害者人口は増加することが予測されています。障害別では、肢体不自由、内部障害が増加傾向にあります。また、通院医療費の給付を受けるため新たに精神障害者と認められるかたの増加が見込まれます。
|
年度 |
平成12年 |
平成17年 |
平成23年 |
|---|---|---|---|
|
総人口 |
317,625人 |
333,109人 |
324,375人 |
|
身体障害者数 |
10,393人 |
12,733人 |
14,086人 |
|
知的障害者数 |
1,337人 |
1,713人 |
1,997人 |
|
精神障害者数 |
2,702人 |
4,882人 |
7,273人 |
施策の概要
社会参加の促進
障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重し相互に支え合う共生社会を実現するためには、障害児(者)が自らの能力を社会のなかで発揮できるような環境にすることが重要です。
障害児(者)は、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自らの能力を最大限発揮する努力をし、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員としてその責任を分担することが求められます。
他方で、障害児(者)の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除き、就業、就労などの機会を確保することにより、障害児(者)が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援することが必要です。
そのためには、行政だけでなく、地域社会の構成員一人ひとりの理解と協力を促進し、地域社会との連帯を保ちながら、その実現を着実に進めていくことが重要です。
保育所における障害児保育
障害児を認可保育所で受入れ、その健全な育成を促進します。
幼稚園における特別支援教育
障害児を幼稚園で受入れ、ニーズを把握しながら発達を促進します。
小・中学校における特別支援教育
小・中学校に特別支援学級を設置し、一人ひとりの適性に応じた指導の充実を図るとともに、通常の学級に在籍する特別な教育的支援が必要な児童生徒に対しても、個別的な支援の充実を図ります。
子ども未来センター運営事業
地域や関係機関と連携し、総合的に子育て支援施策を推進します。
放課後児童健全育成事業
放課後に保護者が家庭にいない児童に遊びや集団生活の場を提供します。
特別支援学校児童生徒の放課後および長期休みのケア
特別支援学校に通う児童生徒が、放課後や学校の長期休みの間、介護を受ける場を確保します。
就学相談
心身に障害のある幼児の就学相談を充実します。
就学時健康診断
就学予定者の心身の状況を的確に把握し、保健上必要な指導助言を行います。
心身障害児就学指導委員会の開催
障害のある幼児・児童生徒の適正な就学について審議します。
特別支援教育就学奨励費
小・中学校の特別支援学級などに入級している児童生徒の保護者に就学奨励費を支給します。
就労のための支援
福祉・労働・教育等の関係機関が連携して支援するため、障害者就労支援ネットワークを構築します。
障害者就業・生活支援事業
生活支援や就労支援等を一体的かつ総合的に行い、地域生活を支援します(県事業)。
知的障害者就労環境支援事業
秋田市リサイクルプラザで作業訓練を行い、一般就労への移行を支援します。
職親制度
職親の下で生活指導および技能習得訓練などを行います。
精神障害者社会適応訓練事業
事業所での訓練を通じて病気の回復と社会復帰を支援します。
雇用の促進および職業の安定
関係機関と連携し、個々の適性と能力に応じた雇用の促進と職業の安定を進めます。
授産施設・小規模作業所への支援
障害者自立支援法による新体系の事業所や地域活動支援センターへの移行や施設の安定した運営を支援します。
市民スポーツの振興
誰もが気軽にスポーツに親しむことができる環境をつくります。
障害者スポーツ大会・教室開催事業
スポーツを通じて社会参加を促進します。
学習機会の提供
学習ニーズやさまざまな課題に応える学習機会を提供します。
保健・医療・福祉サービス基盤の整備
障害者自立支援法の施行により、身体・知的・精神の3つの障害種別に分かれていたサービス体系の一元化や育成医療・更生医療・精神通院医療の自立支援医療への一元化など、大幅な改革が段階的に行われました。
それに応じて、今後、保健・医療・福祉の全般にわたって、できるだけ障害者の求めに応える形で、ハード・ソフト両面から新たな枠組みでサービス基盤の整備を推進しようとするものです。
妊産婦保健事業
妊産婦の心身の健康を保ち、不安なく子育てができるよう支援します。
乳幼児保健事業
子どもおよび家族がより望ましい養育環境を確立できるよう支援します。
特別予防接種等
健康上の理由で通常の予防接種が受けられない子ども等に予防接種を実施します。
訪問支援
精神障害者の状況、家庭環境、社会的環境などの実状を保健師が訪問して把握し、これらに適した支援を行います。
心の健康相談
心の健康に関する正しい知識や対処方法についての助言・指導、関係機関の紹介をします。
生活習慣病予防・介護予防
生涯にわたる健康な生活習慣の確立と、生活機能の維持ができるよう支援します。
介護保険のリハビリテーション
適切なリハビリテーションが行われるよう、事業所に対し情報提供や指導等を実施します。
自立支援医療給付事業
自立支援医療の自己負担分の一部を公費負担します。
福祉医療費給付事業
重度心身障害児(者)や高齢身体障害者等に保険診療の自己負担分を助成します。
療養介護医療
進行性筋萎縮症(進行性筋ジストロフィー)の重度身体障害者に必要な治療および機能回復訓練等を行います。
小児慢性特定疾患治療研究事業
小児慢性特定疾患の治療方法に関する研究を行うとともに、医療費負担を軽減します。
特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。
障害者手帳の交付
障害の程度に応じて福祉サービス等を利用できるよう障害者手帳を交付します。
障害者相談員設置
地域において障害者や保護者からの相談に応じ、必要な指導・助言を行うとともに、障害福祉について啓発・普及活動を進めます。
地域福祉権利擁護事業
判断能力が不十分な知的障害者、精神障害者等に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行います。
特別障害者手当等の支給
在宅の重度障害児(者)に特別障害者手当を支給します。
特別児童扶養手当の支給
中程度以上の障害のある児童を在宅で養育しているかたに特別児童扶養手当を支給します。
療育援助費の支給
心身障害児(者)を在宅で養育しているかたに療育援助費を支給します。
心身障害者扶養共済掛金給付事業
県の心身障害者扶養共済制度への低所得者の加入を支援します。
施設整備の推進
介護を要する居住の場、社会活動や自立訓練、就労訓練さらに地域交流を行うための場を確保します。
地域生活の充実
障害者が日常を安心して暮らし、積極的に社会参加するためには、地域社会の構成員として自ら発言し、理解を求めるとともに、適切に権利を主張することが必要です。
他方、住宅・道路・交通・通信などの生活基盤を適切に整備し、障害者が地域で自立生活するための個別ニーズに対応するサービスを選択できるよう生活環境を整備する必要があります。
また、障害児(者)が自立した地域生活を送るためには、自らの自覚と自助努力が最も重要ですが、地域における支え合いや身近な場所での相談体制、サービスの供給体制などを充実する必要があります。
福祉教育の推進
小・中学校における福祉教育を一層推進します。
教育相談事業
小・中学校、教育委員会の教育相談体制を充実します。
小・中学生と障害児(者)との交流
小・中学生と障害児(者)との交流を推進します。
男女共生社会の推進
誰もが互いの人権を認め合い、一人ひとりが個性や能力を十分に発揮できる社会の実現をめざします。
障害者週間・精神保健福祉運動週間
市民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めます。
精神障害についての正しい知識の普及
精神障害者の社会参加と自立について市民の理解と関心を深めます。
障害者製作製品の周知促進
市主催の各種イベント等における障害者製作製品の展示や販売を支援します。
相談支援等事業
必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援、虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整、障害児(者)の擁護のために必要な援助、ならびに、療育指導等を実施します。
地域自立支援協議会
相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たします。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用について費用の助成などの支援をするほか、手続きの迅速化など市の体制を整備します。
コミュニケーション支援
手話通訳者の設置、手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣のほか、手話奉仕員・要約筆記奉仕員の養成を実施します。
日常生活用具の給付
在宅の重度障害児(者)に障害の内容や程度に応じて日常生活用具を給付します。
移動支援(ガイドヘルパー派遣)
ガイドヘルパーの派遣などにより屋外での移動が困難な障害者の外出を支援します。
地域活動支援センター機能強化事業
創作・生産活動の機会の提供や社会との交流促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化します。
訪問入浴サービス
歩行が困難で、移送に耐えられない等の事情のある在宅の重度身体障害者に居宅での入浴サービスを提供します。
日中一時支援事業短期入所型
介護するかたが一時的に短時間介護できない場合に、宿泊を伴わない施設入所サービスを提供します。
居宅介護(ホームヘルパー派遣)
ホームヘルパー(訪問介護員)を派遣して、身体の介護や家事の援助などのサービスを提供します。
「食」の自立支援事業
在宅の身体障害者に栄養バランスのとれた食事を配食しつつ安否確認を行います。
訪問看護
看護師などが主治医と密接に連携しながら療養生活を支援します。
短期入所(ショートステイ)
介護するかたが一時的に数日間介護できない場合に、施設での短期入所サービスを提供します。
重症心身障害児(者)通園事業
在宅の重症心身障害児(者)に、通園により日常生活動作や運動機能等に係る訓練・指導など必要な療育を行います(県事業)。
難病患者への支援
在宅で療養している難病患者・家族に対し、各種相談・ホームヘルプサービスなど物心両面で地域生活を支援します。
身体障害児(者)補装具給付等事業
身体機能を補うための用具を交付します。
精神障害者社会復帰相談指導事業
地域で暮らす精神障害者の社会参加の場を提供し、社会復帰を支援します。
地域福祉活動の推進
誰もが身近な地域で生きがいを持って自立した生活が送れるよう、ともに支え合い、助け合う地域福祉の充実につとめます。
障害者関係団体等への支援
障害者関係団体等の活動を支援します。
住環境の整備
住宅リフォームの助成など住宅のバリアフリー化を促進します。
グループホーム・通勤寮・福祉ホーム
利用者ニーズの動向等を勘案しながら整備を進めます。
情報提供体制
障害福祉サービスや生活に必要な情報をさまざまな媒体を通じて提供します。
視聴覚障害者への図書館サービス
視聴覚障害者に、図書資料、雑誌、新聞記事等の情報を提供します。
防災体制
災害時要援護者へ配慮した災害予防対策を講じます。
救急救命体制
119番通報の際の障害者へのサポートや民間の患者等搬送用自動車の認定など、救急救命体制を充実します。
緊急通報システム
急病や緊急時に迅速かつ適切に対応できるよう、緊急通報装置を貸与します。
バリアフリーによるまちづくりの推進
公共施設や公共交通機関のバリアフリー化を促進します。
障害者バス無料化事業
市内の路線バスを無料で利用できるよう福祉特別乗車証を交付します。
通院移送費給付事業
重度身体障害児(者)が通院に利用するタクシー料金の一部を給付します。
福祉有償運送
公共交通機関を利用することが困難な重度の障害者および要介護者の交通手段を確保します。
自動車運転免許取得費、改造費助成事業
身体・知的障害者が自動車運転免許を取得する費用や、身体障害者自らが所有し運転する自動車の改造費用の一部を助成します。
サービス提供の目標および見込み
必要な障害福祉サービス等が地域において計画的に提供されるよう、本市における平成23年度末までの目標および見込みを、次のとおり設定します。
地域生活・一般就労への移行
入所施設の入所者の地域生活への移行
- 平成17年10月1日現在の入所者数(A):579人
- 平成23年度末時点の入所者数見込(B):534人
- 削減見込(A-B):45人(7.77%)
- 地域生活への移行をめざす数(平成23年度まで):42人(7.25%)
入院中の精神障害者の地域生活への移行
- 現在の退院可能精神障害者数(平成17年推計):116人
- 地域生活への移行をめざす数(平成23年度まで):86人
福祉施設の利用者の一般就労への移行
- 平成17年度の一般就労への移行者数:4人
- 一般就労への移行をめざす数(平成23年度):16人(4倍)
指定障害福祉サービス等
訪問系サービス(単位:時間分/月)
| 区分 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|---|
| 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・重度障害者等包括支援 |
3,553 |
3,945 |
4,425 |
6,651 |
障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を推進するため、行動援護や重度訪問介護、重度障害者等包括支援といった新規サービスに関し周知を図り、特に精神障害に対応する事業者の参入を促し、サービス量の確保に努めていきます。
日中活動系サービス(単位:人日分/月)
| 区分 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|---|
| 生活介護 |
1,056 |
8,206 |
11,132 |
19,910 |
| 自立訓練(機能訓練) |
154 |
264 |
418 |
792 |
| 自立訓練(生活訓練) |
616 |
2,134 |
2,816 |
5,192 |
| 就労移行支援 |
0 |
792 |
924 |
1,298 |
| 就労継続支援(A型) |
0 |
44 |
176 |
924 |
| 就労継続支援(B型) |
0 |
3,366 |
4,928 |
11,374 |
| 療養介護(単位:人分/月) |
27 |
27 |
27 |
27 |
| 児童デイサービス |
0 |
10 |
12 |
18 |
| 短期入所 |
85 |
115 |
155 |
335 |
事業者の新体系への移行状況や利用者のニーズの把握に努め、事業者へはスムーズに新体系サービスに移行できるよう支援し、サービス量の確保に努めていきます。また、就労支援については、事業者、企業およびハローワークなど関係機関と連携を図り、就労支援の強化に努めていきます。
居住系サービス(単位:人分/月)
| 区分 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|---|
| 共同生活援助・共同生活介護 |
78 |
110 |
127 |
210 |
| 施設入所支援 |
0 |
258 |
343 |
534 |
障害者の地域移行を進めるために共同生活援助や共同生活介護の計画的な推進が必要となることから、今後の地域移行の状況を把握し、地域の理解を深め、適切なサービス量の確保に努めていきます。
その他のサービス(単位:人分/月)
| 区分 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|---|
| 相談支援 |
9 |
12 |
17 |
36 |
利用者の意向や心身の状況などをふまえ、一人ひとりのニーズに応じた支給決定を行うため、相談支援専門員の資質を高めるとともに、地域自立支援協議会の活用を図りながら、良質なサービスの提供に努めていきます。
注:ここでの相談支援とは、自ら障害福祉サービス利用に関する調整が困難な単身生活者などサービス利用計画書の作成が必要な方を対象としたものです。
地域生活支援事業
障害児(者)が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の実情や利用者の状況に応じて市が柔軟に実施できる事業です。本市では、以下の事業を実施します。
実施する事業内容
事業名:相談支援事業
- 事業内容
- 相談支援事業(障害者相談支援事業、地域自立支援協議会、障害児等療育支援)、市町村相談支援機能強化事業、住宅入居等支援事業、成年後見制度利用支援事業
事業名:コミュニケーション支援事業
- 事業内容
- 未定
事業名:日常生活用具給付等事業
- 事業内容
- 介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
事業名:移動支援事業
- 事業内容
- 未定
事業名:地域活動支援センター
- 事業内容
- 基礎的事業、機能強化事業
事業名:その他の事業:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、更生訓練費給付事業、更生訓練費給付事業、日中一時支援事業
- 事業内容
- 未定
事業名:その他の事業:社会参加促進事業
- 事業内容
- スポーツ・レクリエーション教室開催等事業、点字・声の広報等発行事業、奉仕員養成研修事業、自動車運転免許取得事業、自動車改造助成事業、ボランティア活動支援事業
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
