平成29年度 秋田市エイジフレンドリーパートナー研修会
平成29年10月19日(木曜日)、市民、民間企業、教育機関、行政機関の連携による、超高齢社会のニーズに対応したまちづくりについての知識と意識の向上を目的に秋田市エイジフレンドリーパートナー研修会を開催し、パートナー事業者・団体のほか、超高齢社会におけるビジネスや地域社会づくりに関心のある市民が参加しました。
参加者からは、「長寿社会の現状の再認識と将来への備え方について考える機会になった」、「(リビング・ラボについて)高齢のお客様がどのようなモノが使いやすいかを訊きたい」、「理学療法士としての自分の知識を活かして、自治体、企業等と合わせて仕事ができれば、働き方の幅が非常に広がると思った」等の声をいただきました。
- 参加者数
-
125名(定員150名)
- パートナー事業者・団体
-
51名(42社)
- 一般
-
74名
プログラム
秋田市エイジフレンドリーパートナー取組事例発表
他社が実施するエイジフレンドリーな取組内容を学び、自社の取組の更なる充実化を図るため、秋田銀行と秋田キャッスルホテルが、それぞれの取組内容を発表しました。
要旨
秋田銀行 経営企画部 小濱 俊氏
パートナー第1号として、平成27年5月1日に登録。「あきぎん長活き学校」、「秋田プラチナタウン研究会」等の運営に取り組んでいる。
あきぎん長活き学校
超高齢社会の先進地秋田県において、いきいきと活躍するアクティブな高齢者を創出するために、講演会やディスカッション、課外授業などを行っている。
秋田プラチナタウン研究会
人口減少や少子高齢化を解決し地域活性化を図るため、産学官民のオール秋田が連携する場である。当研究会の一環として、秋田駅東口における「スポーツ・健康を通じて多世代が元気に暮らせる地域づくり」をコンセプトとしたCCRC事業があげられる。
目指す秋田市の姿
「あきぎん長活き学校」でアクティブシニアを創出し、「秋田プラチナタウン研究会」で高齢者が元気に暮らせるコミュニティづくりを推進することにより、高齢者の社会参加の促進と、高齢者が長く活躍する地域社会の実現を図るとともに、消費拡大による地域経済の活性化を図る。
秋田キャッスルホテル 営業部宴会セールス課 支配人 加藤 乃武雄氏
パートナー第3号として、平成27年6月3日に登録。安全、快適、接客マナーにおいて「あらゆる世代にとってやさしい」ことに加え、お客様に「楽しんでいただける要素」を備えた「エイジフレンドリーホテル」を目指している。
取組事例
車いす使用のかたからのご意見に基づいた多目的トイレの改修、従業員による認知症サポーター養成講座の受講、高齢者から子どもまで三世代が楽しめるイベントの企画などに取り組んでいる。
平成28年秋田県バリアフリー推進賞を受賞
ハード(設備面)、ソフト(認知症サポーター養成講座等)両面におけるバリアフリーが評価され、平成28年秋田県バリアフリー推進賞の「活動部門」を受賞した。



基調講演「産学官民による長寿社会のまちづくり」
老年学研究の第一人者である、東京大学高齢社会総合研究機構(以下、東大IOG)の秋山 弘子特任教授を講師に迎え、東大IOGが携わる千葉県柏市におけるまちづくりや、神奈川県鎌倉市の「鎌倉リビング・ラボ」を事例に、長寿社会の課題と対策および産学官民の連携の重要性について講演を行っていただきました。
講演資料

東京大学高齢社会総合研究機構 秋山 弘子特任教授
イリノイ大学でPh.D(心理学)取得、米国の国立老化研究機構(National Institute on Aging)フェロー、ミシガン大学社会科学総合研究所研究教授、東京大学大学院人文社会系研究科教授(社会心理学)、日本学術会議副会長などを歴任。専門はジェロントロジー(老年学)。高齢者の心身の健康や経済、人間関係の加齢に伴う変化を25年にわたる全国高齢者調査で追跡研究。近年は超高齢社会のニーズに対応するまちづくりや、産学官民協働のリビング・ラボにも取り組む。超高齢社会における、よりよい生のあり方を追求している。
要旨
長寿社会の課題と対策
長寿社会の3つの課題
-
個人の課題
-
人生100年の人生設計を自分で作らなければいけない(先行モデルがない)。
-
社会の課題
-
長寿社会に合わせ、現在の社会インフラを見直さなければいけない。
-
産業界の課題
-
人生100年時代に対応するモノやサービス、インフラづくりを産業界がリードしなければいけない。
高齢者追跡調査から見える対策
- 75歳以降自立が難しい傾向があるが、元気な自立期間を80歳まで延ばす取組が必要(個人的にも社会的にもメリットが大きい)。
- 支えが必要になった場合、住み慣れた地域で日常生活の継続を可能にする環境の整備が必要。
- 社会の中に、人とつながる仕組みをつくることが必要(特に高齢男性は孤立しがち)。
千葉県柏市におけるまちづくり
目的と概要
「自立期間の延長」、「支えが必要になった場合の環境整備」、「人とのつながりづくり」を掲げて、長寿社会のまちにつくりかえる社会実験を行っている。その一つとして、千葉県柏市の豊四季台団地(50年ほど前にできた5000戸の大きな団地であり、現在の高齢化率は40%)を拠点に、周辺地域を含めてさまざまな取組を行い、柏市全体に広げる構想である。
高齢者の就労についての意識と柏市におけるセカンドライフの就労の場づくり
- 次期高齢者(50~64歳)を対象とした、「65歳以降にやりたいこと」というアンケート結果によると、「働きたい」という回答が1位である。
- 厚生労働省のリサーチによると、高齢者の就労率が高い県は、一人あたり高齢者医療費が低いという相関が出ている。
- 農業、食堂、保育、生活支援、福祉などの分野で就労の場づくりを実施。自分で時間を決めて働くことができるワークシェアリングの導入など、セカンドライフにふさわしい柔軟な働き方を取り入れている。
生涯現役地域促進事業
- 高齢者の雇用・就業機会を創出する取組に対し、厚生労働省の「生涯現役地域促進事業」を活用することができる(平成29年11月30日現在、募集は終了している)。
- 当事業により、柏市では就労を含めたセカンドライフ設計の相談ができる窓口を設置。また、未経験分野への就労支援も行っている。
住み慣れた地域で安心して暮らせる環境整備
- ライフステージに応じた住み替えを可能にする循環型住宅の供給。
- 医療・介護・他職種連携による地域包括ケアシステムを整備。
- 主治医による訪問診療を進めるため、副主治医専門の医師によるバックアップの体制により、主治医の負担を軽減。
- 市役所が事務局となり、医療をはじめとした各関係職種のワーキンググループをつくり、定期的に話し合いを実施。
- 既存のICTを使い、関係者が情報連携する共通基盤を構築。
産業界との連携
東京大学IOGと産業界との連携事業
2009年に設立した「ジェロントロジー・コンソーシアム」では、東大が企業にジェロントロジー(老年学)各分野の知識・技術を提供し、超高齢社会に必要な新たな産業の創成を目指している。さまざまな業種から53社が参加。
高齢者市場とニーズ
- これまでのシニア市場は、「要介護層」(1割)および「裕福層」(1割)を対象としており、そのほかの「普通層」(8割)は未開拓。
- 団塊シニアは自分の自立のために投資をする傾向があるため、住宅リノベーションや、ロボット・AI技術等、産業界のイノベーションが必要。
- 高齢者のニーズは、年齢に応じて「社会で活躍したい」「自立生活を継続したい」「住み慣れた地域で最期まで暮らしたい」と変化。
鎌倉リビング・ラボ
リビング・ラボとは、産学官民など多様な関係者が連携し、市民(ユーザー)の暮らしに役立つ製品・サービスや技術を創り出す活動。
概要
- 鎌倉市の今泉台(高齢化率40% 人口5000人)が拠点。
- 東京大学IOG、鎌倉市役所、今泉台の住民、企業(ジェロントロジー・コンソーシアム)、三井住友銀行が連携。
- 住民・自治体・企業が抱える課題に基づき、ラボ活動を実施。
国際連携型のリビング・ラボ
- 企業は、従来の自己完結型のマーケットリサーチではなく、オープンな場でのイノベーションにシフトする傾向がある。
- EUはアジアの高齢者市場(世界の高齢者6割がアジア)に関心が強く、日本のリビング・ラボを活用し、アジアの人々に適した製品・サービス開発を考えている。一方、日本の産業界は、ヨーロッパの高齢者市場に関心があるため、今後は日本・EU双方の国際的な連携が重要になると考えられる
長寿社会の課題と可能性
- 地域社会に若い人を呼び込むことのみに注力するのではなく、高齢者が多い社会でいかに快適に経済を回していくかを考えていかなければいけない。
- 異なる組織・立場から協働する体制をつくるのは難しいことであるが、産学官民の横連携が実現するとさまざまな物事が進みやすくなる

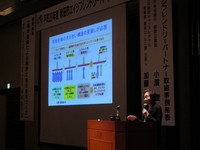

質疑応答
質問1:柏市では、シニアの就労場所の洗い出しも、生涯現役地域促進事業に含んで実施しているのか。
回答1:柏市は農業、鎌倉市は観光というように、地域ごとに異なる就労の場をつくることができる。また一方、市役所や学校などの業務において、管理部門をアウトソーシングするなど、どの自治体でも共通してできることもある。このような就労の場づくりに、生涯現役地域促進事業の支援を活用することができる。
質問2:海外の企業が日本の高齢者市場に関心を持っているとのことだが、どのような製品を日本に売り込みたいのか。
回答2:長寿社会の課題を解決できるような、健康、金融、住宅、食品の製品・サービスなどが考えられる。長寿社会のものづくりについて、産業界全体で取り組んでいるのは日本のみであり、今がチャンスである。
質問3:高齢者就業率が高くなると、高齢者医療費が下がるとのことだったが、これを実現するためにはどうすれはよいか。
回答3:一つは、生涯現役地域促進連携事業を利用して、セカンドライフの就労の場をたくさん作っていくこと。そしてもう一つは、高齢になっても社会とつながっていくというポジティブな意識を持ち続けること。就労に関しては、一日短時間でも仕事ができるような働き方のシステムをつくることが大切である。
質問4:秋田では集合住宅よりも持ち家が多いが、ライフステージに応じた住み替えを可能とする循環型住宅について、どのように取り組めばよいか。
回答4:家を手放すのには非常に抵抗があると思う。よって、持ち家を貸して、その賃料で自分に適したサイズの家や集合住宅を借りるのがよいのではないか。循環型の住み替えができるような、家・集合住宅を供給できることが重要。


PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 長寿福祉課 エイジフレンドリーシティ推進担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5666 ファクス:018-888-5667
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
